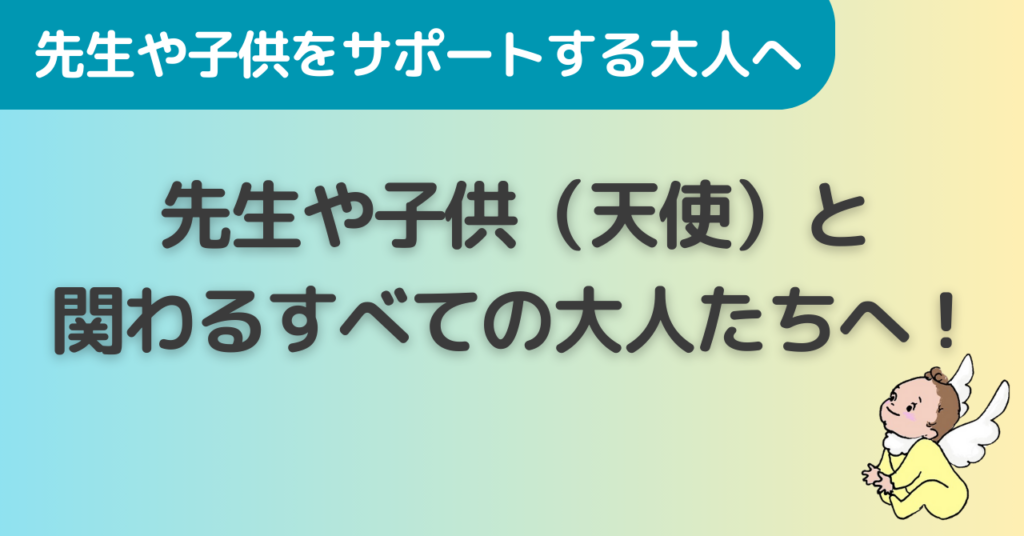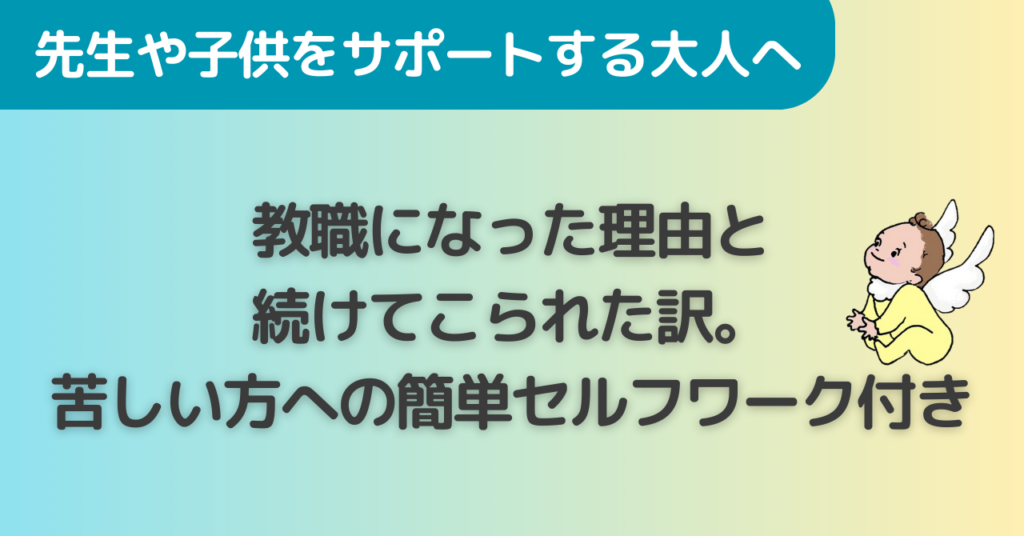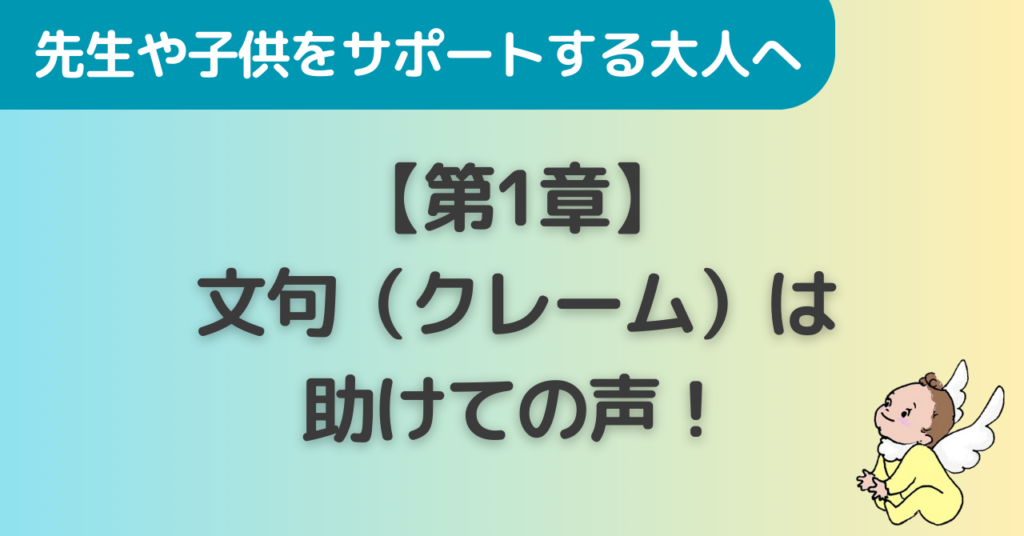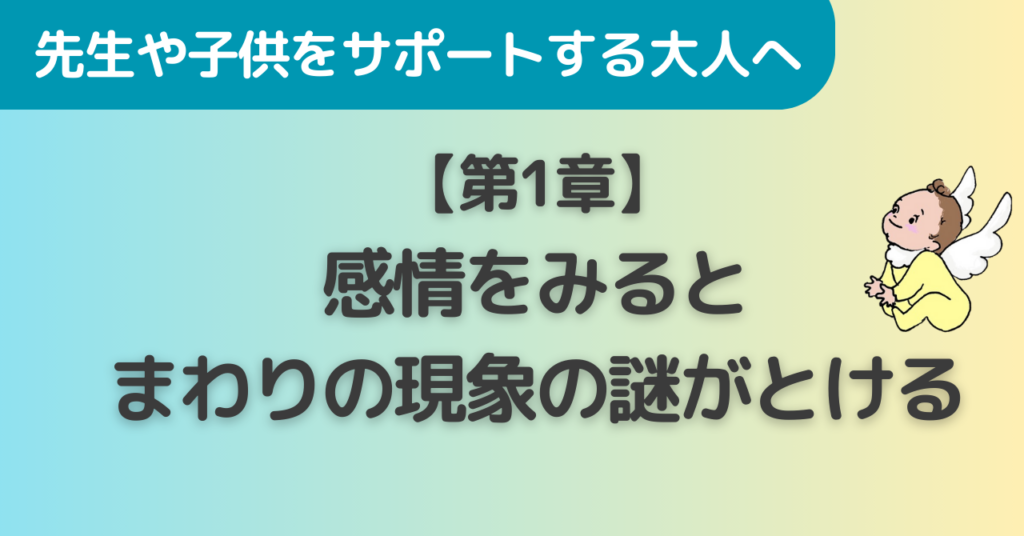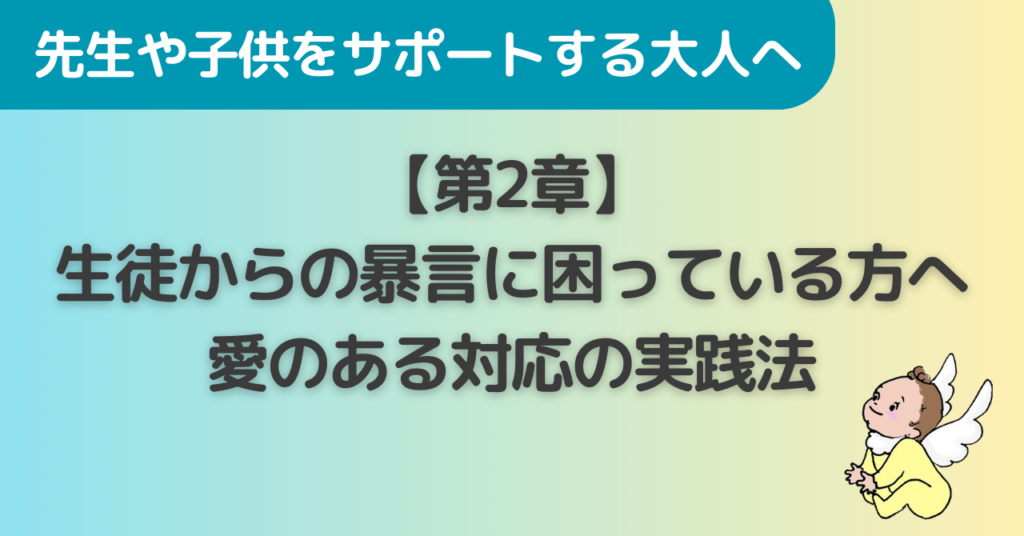
こんにちは、かずみんです!
関わりが難しい子の心が、なかなかつかめない
関係がうまくいかない…
という体験は、先生ならば多くの方が経験すると思います。
私自身もよくありますし、今でもそう感じるときがあります。辛いですよね。
特に多いのが、生徒からの『担任の先生への暴言』です。
先生側としては、正当な理由で注意をしていても、たいていは聞かないことが多いですよね。
そんな時、昔はよく、うまくできない自分の未熟さに腹が立って、イライラしていました。
または、「ちゃんと言うことを聞かないのが悪い!」とその子やその子の親のせいに感じることもありました。
でも、何年も向き合い実践する中で、うまくいく方法をいくつか見つけることができたのです。
今日は、
- 暴言を吐く子供に出会ったことがある
- 今まさにそのような子供と関わっている
という方へ向けて、私が実際にうまくいったリアルな方法をお伝えしようと思います!
1、『暴言』の裏にある子供の”本当”の心理
そもそもなぜ、担任や先生たちにそのような態度で接してくるのでしょうか?
簡単にいうと、『甘えている』わけです。
本当に嫌いだったら、関わらないはずですなのです。
でも、逐一担任の行動を見ていて、そこでわざわざ暴言をいうわけですから、何らかの形で『関わりたい』と思っているんですね。
もっというと、本当は”よい言動で関わりたい”と思っています。
でも、これまでの何かの経験で、
「自分はよい態度では注目してもらえない」
「悪い態度をすると注目される・関わってもらえる」
と間違って学習してしまった可能性が高いと考えられます。
または、単純に甘え方がわからなかったり、「助けて」が言葉で言えない、というケースもあります。
2、間違って学んでしまった「愛されるため」の行動
同じような状況が、その子の家庭内でも起こっているはずです。
多いケースとしては、親が弟や妹ばかりに関わっていて、長男・長女がやきもちを焼く。
自分も甘えたいのに、どうやって甘えたらいいかわからず、妹や弟に手をあげたら親にしかられ、結果的に親の注目を得られた。
そうやって、悪いことをすると、親が自分の方を向いてくれる…と勘違いするパターン。
他にも、病気になったら、心配して注目を得られたパターン。
学校で問題を起こしたら、注意を向けてくれたパターン…。
など、ただ甘えたい・注目されたい・優しくされたいだけなのに、
いろいろと複雑な行動をしないと親からの注目が得られない、愛されないと勘違いして学んでしまった子供がいるのです。
子供は、いつでも親の愛情がほしいと思っています。
それを得るためには、自分を傷つけることを厭わない場合もあるのです。
3、言動が悪い子供とうまく関わる3つの方法
ここまで読むと、なんとなくその子の見えなかった心理がわかってきたのではないでしょうか。
学校で暴言や悪い態度をとるというのは、一番は親へSOSのサインです。
しかし、家庭で受け入れてもらえない場合、次に受け入れてくれそうな人(先生や学校)にそのサインを向けることもあります。
そんな見方をしていくと、彼らはただの問題児ではなく、
「未熟な愛情表現をしている子供」
「助けを求めている子供」に見えてきませんか?
とはいえ、毎日暴言を浴びせられるのは、きついですよね。
大人だって傷つきます。
そんな時、試して欲しい方法が3つあります。
実際に私が取り組み、うまくいったことだけを書きますね!
❶「助けを求めている」ことに気づく
1つ目は、さっきも書いたように、
- 愛情を受けたいのに受けられず困っているんだ
- 助けを求めているんだ
と思うようにすることです。
「これは助けを求める声」なんだ。私を攻撃したいわけではない。
伝え方がわからないだけなんだ、と自分自身に言い聞かせることです。
❷一人で抱えず周りの人に助けてもらう
2つ目は、自分自身が『周りの人に助けを求める』こと。
一人で抱え込んでしまうのが、一番よくありません。
あなたが今抱えている問題や「どうしたらいいかわからない」という気持ちを、先生チームや信頼できる人に分かち合いましょう。
あなた一人ではなく、たくさんの大人の中でその問題を共有します。
一人ではできなくても、チームで関われば良い方法が思いつくかもしれませんし、何よりあなたの心の支えになります。
❸ユーモアを持ち込む
3つ目は、ユーモアです。
子供からの暴言には、ユーモアで返すのが一番です。
例えば私の場合、「ばばぁ」とよく言われるのですが、
「おばさんにばばぁと言って、何が面白いのですか?それは、事実ですよ(笑)」と言い返します!
「ただ、今は先生という仮面をかぶっているので『先生』と呼んでほしいです。でも、お面の下に隠しているおばさんを見抜けるなんて、素晴らしい目を持っていますね!」
という風にまともに受けるのではなく、ユーモアで返します。
子供は、先生を怒らせようとしているのに、動じない態度をみて、言っても意味がないことをだんだんと感じとります。
ちゃんと「先生」と呼んだ時には、「はい、先生です!何か御用ですか(笑顔)」と反応します。そして、近づいていって優しい言葉で関わります。
傷つく言葉を発した時には、胸のところを抑えて倒れこみます。
これは、担任にだけでなく、友達に言ったときにもです。
しばらく黙り込み、すごく傷つくことを言葉でなく態度で教えます。
言った子供に注意をするのでなく、「暴言がどれくらい傷つくことか」を伝えるためです。
4、さあ、変化を起こしてみましょう!
これらは、あくまで一例です。
もちろん、暴言はいけないし、人を傷つける言葉はきちんと指導しなければなりません。
ただ、怒られ慣れている子供にとっては、売り言葉に買い言葉。
毎日同じやり取りをしていると、先生の方は疲弊してしまいますよね。
そこで、どう反応したら、その子供をあんぐりさせられるかを考えた方が楽しくないですか?
もちろん、緊急で危険な時には、このような方法は使いません。
ただ、誤学習のやり取りが続いているときは、こういった方法を使ってみると変化が起こるかもしれません。
前にもお伝えしましたが、目の前の子供は、あなたを成長させるために存在してくれている大切な子供なのです。